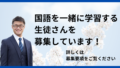サピックスに通う生徒さんのご家庭からよく聞く悩みがあります。

算数や理科は勉強の方法がわかるけれど、国語Bテキストはどう勉強すればいいのかわからないんです……
国語B授業では主に記述問題を扱いますが、お子さんの答えが模範解答とまったく同じになることは基本的にないため、「どのように勉強すればいいのか……」と悩んでしまうのですね。
この記事では、サピックスの国語B授業の家庭学習(宿題)の進め方、偏差値60を目指すためのポイントを説明します。別の記事「【サピックスの国語】偏差値60の壁を超えるための勉強法と覚えておきたい重要事項」と合わせてお読みいただければと思います。
国語B授業とは? そもそもどのような教科なのか
国語B授業はそもそもどのような教科なのでしょうか。私はこう考えています。

長文を読むなかで社会を生きる人としての教養を身につけながら、論理的思考力と記述力を養う教科。
国語B授業では長い文章が出されます。特に物語文では10ページ以上の文章が取り上げられることもあり、読むだけでもパワーと時間が必要です。その文章を論理的に読み解き、主に記述問題に取り組むのが国語B授業の特徴です。
では、上記の「社会を生きる人としての教養を身につけながら」というのは、どのようなことでしょうか。
国語B授業のテキストでは文学的文章(物語文)、説明的文章(説明文、論説文)、随筆文、詩が扱われます。そして、それらの文章・詩はさまざまなことがテーマとなっています。
「親子の愛情」「友情」「同情」「差別」「貧困」「障害」「病気」「命」「戦争」「紛争」「環境破壊」「科学技術」「自然科学」「建築」「美術」「個性」などなど……。いずれも小学生にとっては難しい内容であるいっぽう、社会を生きる大人としては最低限の教養として身につけておきたいことばかりと言っていいのではないでしょうか。国語Bではこれらをテーマにした文章を読みながら、理解を深めていくことが大切です。
こんなお話をすると、次のように感じる方がいらっしゃるようです。

大人でも難しいのに、子どもにはなおさら難しいような気がするんですけど……。
本当におっしゃる通りですよね。私も「小学生にとっては本当に難しいなあ」と感じます。しかしながら、国語Bの文章で取り上げられるテーマは、いずれも中学入試の頻出テーマです。つまり、私立中学・国立中学の先生方は「未来の社会を生き抜く最低限の素地を身につけた受験生に入学してほしいと願っている」のではないかと、私は考えています。
そうだとすれば、がんばって取り組むほかありませんよね。特に今回の記事の趣旨である「サピックスで偏差値60を目指す」のであれば、避けて通ることはできないなと感じます。毎回の授業で配られるテキスト一つひとつに真摯に取り組み、力をつけていきましょう!

中学受験の目標はもちろん、第一志望校の合格ですよね。ただ、どのお子さんもその過程で大きく成長していきます。中学受験に出題される文章のテーマ(つまり、国語B授業のテキストで取り上げられるテーマ)は、お子さんの成長をうながすものになると考えています。
国語Bテキストの構成と傾向
サピックスの国語Bテキストは、平常授業で使用される教材です。読解力や記述力を養成するための中心的な教材だと言っていいでしょう。「本文」「問題」「解答・解説」の3冊1組となっており、毎週の授業ごとに1セットずつ配布されます。特徴は以下の通りです。
- 文章読解がメイン(物語的文章、説明的文章、随筆文のバランスがよく計画されている)
- 記述問題が豊富(偏差値60を目指す上で必須となる記述力を身につける)
- 語彙力や背景知識も試される(読解力・記述力を伸ばすには、語彙力や社会のことに対する理解も重要)
偏差値60を目指すのであれば、記述問題に取り組むなかで本文の内容を論理的にとらえ、理解したことを表現する力を養うことが必要です。物語的文章、説明的文章、随筆文を選り好みせずに、好奇心を持って積極的に取り組む姿勢を持ちたいですね。
また、物語文に描かれた人物の心情・気持ち、人物やストーリー全体を通して描かれた作家先生の主張・考え方、物語全体のテーマ・世界観を自分なりに受け止めて、自分の世界を広げていく姿勢を大切にしましょう。これは説明的文章に書かれた筆者の主張、社会や世の中のことについて読むときも同じだと考えるといいですね。
ここで大事なのは、自分とは異なる心情や意見に出会ったときの姿勢です。
「自分には関係ない」「自分にはわからない」と考えずに、「そういうふうに感じる人もいるんだ」「こういう考え方もあるんだ」と素直に受け止められるかどうか。この姿勢が学力・成績を伸ばすことにつながります。
国語Bの家庭学習の手順と取り組み方|サピの先生から図解するように言われたらどうする?
サピックスで授業を受けただけでは、せっかく理解したことも忘れてしまいます。授業で理解したことを定着させ、深めていくために、家庭学習には必ず取り組みたいですね。
家庭学習にかける時間は60〜90分を目安にするといいでしょう。「サピックスの授業と同じくらいの時間を復習に充てればいいのだな」と考えるといいですね。いっぽう、この時間を超えてくるようだと、ちょっと長すぎです。サピックスの先生や家庭教師、個別指導の先生に相談して、学力に合わせた量に調整してもらうといいですね。
- 本文を読み直すことからスタート
- 授業で解いてきた問題を読み、どこに気を付けて答えを考えるべきか確認する
- 本文の該当箇所(傍線部や空欄など)を確認する
- サピックスの先生から「図解を書くように」と指示があったら?
- 授業で解いてきた問題を自分で書き直す(書き直すときの注意点やポイントもまとめています)
- 保護者と一緒に答え合わせをする
- サピックスで解いてこなかった問題にも取り組む
- 文章のテーマについて、親子で話し合う
本文を読み直すことからスタート
こんなことを言うお子さんがいます。
昨日の授業で読んだばっかりだから、読み直さなくても覚えてる!
本人は覚えているつもりでも、授業を受けてから時間が経っていますので、記憶は曖昧になっています。その状態で復習に取り組もうとしても「読解」できません。必ず本文を読み直してから家庭学習をスタートしましょう。

音読が家庭学習になっている場合は、このタイミングで取り組むといいですね。大切なことは保護者の方が音読を聞いていることです。イントネーションのおかしなところや漢字、熟語、外来語などの読み間違いがあったら直してあげてください。
授業で解いてきた問題を読み、どこに気を付けて答えを考えるべきか確認する

国語B授業のテキストには多くの記述問題が掲載されていますが、授業時間などの都合上、すべての問題に取り組んで帰ってくることはほとんどありません。家庭学習に取り組むときは、サピックスの授業で取り組んできたものを優先しましょう。
設問は解答のヒントの宝庫です。設問を読むことで、問われていることは何なのか、どのように答えればいいのか、条件は何なのかなど、答えを考えるのに大切なことがわかります。
たとえば、以下の問題を見てみましょう。
傍線部B「ありがとう」とありますが、傍線部A「ありがとう」のときとの違いをふまえて、傍線部Bのときの「わたし」の様子を説明しなさい。
これを読むと、たとえば以下のようなことが読み取れます。
- 問われていることは「傍線部Bのときの『わたし』の様子」だな。
- そうだということは、傍線部Bのときの「わたし」の様子を答えの最後に書けばいいな。
- 文末は「~様子。」だな
- 条件は「傍線部Aのときの『わたし』のときとの違いをふまえて」だから気を付けないといけないな。
- そうだということは、傍線部Aのときの「わたし」の様子を先に書いてから、傍線部Bのときの「わたし」の様子を書く構成になりそうだな。
- 傍線部にはいずれも「ありがとう」とあるので、一般的に考えれば「感謝している様子。」という答えになる可能性が高いな。
設問をざっと読むだけでも、これだけのことがわかります。設問を中途半端に確認したり、早合点したりして問題に取り組もうとする受験生はよくいますが、これでは問題を解く力がいくら高くても答えを出せません。まずは問題をしっかり理解したいですね。
本文を読んだあとは必ず設問を読み直し、解答のヒントをつかみましょう。サピックスの先生から設問についての説明があったと思いますので、ノートを読み直しながらどこがポイントだったのかを確認するといいですね。

サピックスの授業中は先生の話をよく聞きながら考えるのとともに、ノートをしっかり取ることが大切です!
本文の該当箇所(傍線部や空欄など)を確認する
本文の傍線部を確認して、指示語や接続語、本文の内容などをヒントに答えを探っていきます。サピックスの授業中にノートを取ってきているはずなので、どうして本文の「その場所」に答えあるいはヒントがあるのかを思い出しながら確認するといいですね。

特に傍線部や傍線部を含む一文に指示語や接続語がある場合は、非常にわかりやすいヒントです。それらに注目するだけで正解に向けた一歩目を踏み出せることが多くありますよ。正解を出すには、以下にはじめの一歩を正しい方向に踏み出すかが大切です!
サピックスの先生から「図解を書くように」と指示があったら?
サピックスの先生から、答えまでの道筋を図に書くよう指示が出ることがあります。基本的にはサピックスの先生が板書するような図を自分で書いてみればいいのですが、途方に暮れてしまうご家庭も多いようです。

図解ってどうやってすればいいの……?
受験生本人が図解をするのは確かに難しいのですが、解答までの道筋を論理的に理解するのに役立ちます。たとえば以下のように図解してみるといいですね。Pは「ページ」、LはLINEつまり「行」を表しています。
■傍線部Aの「ありがとう」
P●L●:「XはYから目をそらして言った」
P●L●:「『じゃ、私、もう帰るから』」「Xは足早に駆けていった」
=XはYと一緒にいるのが嫌だ。
「ありがとう」と言って会話を終わらせたい。早くこの場から離れたい。
★↑なぜ??
P●L●:「いまは自分のことで精いっぱい。人の相手をする余裕はなかった」
=Xは落ち込んでいて心に余裕がなかったから。
■傍線部Bの「ありがとう」
P●L●:「XはYに笑顔を向けた」
=感謝する気持ち
★↑なぜ?
P●L●:「Xの心がこの空のように澄み渡っていくのを感じた。
=落ち込んでいるXを心配したYが景色のいい場所に連れてきてくれた。
そのおかげでXの気持ちが晴れたから。
図解するときのポイントは、以下の2つです。
- 根拠となるページ・行をはっきりさせること
- 要素と要素の関係性がわかるような図にすること(上記の図例にはありませんでしたが、「理由と結果」を表すのなら「→」の矢印を使ったり、「反対・逆」を表すのなら「⇔」の矢印を使ったりするといいですね)
授業で解いてきた問題を自分で書き直す
記述力は「書く」ことで伸びます。授業で扱った問題をもう一度自分で解き直しましょう。その際の注意点は以下の通りです。
答えを書き直すときに意識したいことは?
記述問題の答えを書くときに意識しておきたいことはこちらです。

本文を読んでいない人が自分(受験生)の書いた答えを読んで意味がわかるか?
多くの受験生は、自分が考えたことを文に書くのが苦手です。自分では正しく書いているつもりでも、主語や述語がねじれていたり、説明がなかったりなどで、よくわからない文になってしまっていることは珍しくありません。
しかし、「これでは伝わらないよ。何が書かれているかわからないよ」と伝えても、自分では正しく書いたつもりでいるため、「何が悪いかわからない!」「それぐらい書かなくてもわかるじゃん!」と反発する気持ちが起きることが起きることもよくあります。
自分の書いた文を客観的に見直し修正するのは難しいものです。文を書くことを生業にしている記者やライターの方々でも人から自分の文章の問題を指摘されたり、客観的な目で修正しなければならなくなったりすると心が折れそうになることがあることを考えれば、小学生である中学受験生が嫌になってしまう気持ちもよくわかります。
ただ、自分の答えを修正することで問題点を認識できますし、次の解答へ活かせます。なんとかがんばってほしいですよね。
そこでまずは、いきなり細かいところをバシバシ指摘するのではなく、「本文を読んでいない人があなたの書いた答えを読んで意味がわかるかな?」と伝えみるといいかなと思います。
たとえば、以下のような文をお子さんが書いたとします。
それが多かったから、うれしくなった。
こう書いたお子さんは本文を読んでいるため、「それ=(たとえば)潮干狩りで取れたアサリ」だと知っています。ところが、この文を読んだことがない人はそうではありません。ですから、「本文を読んだことがない人は、『それ』がアサリだってわからないんじゃない? アサリに書き直してみたらどう?」というように促してあげるといいですね。
そして、特に国語の苦手な子であれば、「これができたらOK!」と考えて、次の問題に進んでもいいかもしれません。

完璧を目指してあまりに細かく指摘すると受験生本人のやる気低下や反発につながってしまうことがあります。記述問題の修正とモチベーション維持のバランスを取れるように注意したいですね。
サピックスで解いてきた問題を直したら、保護者と一緒に答え合わせをする
解き直しはサピックスで解いてきた問題を優先します。解き直したあとは答え合わせをしますが、しばしばこのようなことが起こります。

子どもが自分で丸つけしたら全部○になってた…
よくあることです。答え合わせはお子さんと保護者が一緒におこないますが、丸つけは必ず保護者の方がおこなってください。このときに大切なのは「模範解答と比べて何が足りないか」を確認することです。ただし、「ふーん、これも書かなければいけないんだねー」で終わってしまうのではなく、「本文のここにこう書いてあるから、これも書かなければいけないんだね」「なぜ、ここも読まないといけなかったんだろう」というように、一つひとつを確認していくことが重要です。答え合わせをしたら、最後に必ずもう一度書き直してみましょう。
ただし、家庭で完璧にやるのは難しい部分もあります。わからない問題は質問教室や家庭教師の先生に頼ってOKです。

具体的な確認ポイントについては、次の大見出し以降にまとめます。
サピックスで解いてこなかった問題にも取り組む
授業で扱わなかった問題の優先度は低めです。ただし、今回の記事のテーマである「国語で偏差値60を目指す」という観点から、必ず取り組むものだと考えるといいですね。
文章のテーマについて、親子で話し合う
この記事の冒頭で、国語B授業についてこのように紹介しました。
「長文を読むなかで社会を生きる人としての教養を身につけながら、論理的思考力と記述力を養う教科
国語B授業で扱うテーマは小学生にとって難しいものです。その難しいテーマについての理解を深めるには、テキストの文章だけは不十分だと考えられます。
お母様、お父様のご協力が必要です。ぜひ毎回のテキストの文章を読んで、そのテキストのテーマについて親子で話し合う機会を設けてください。
たとえば、あるテキストには障害を抱えた人物が同情されることに対して抵抗を覚える様子が描かれた文章が掲載されています。これに対してお子さんがどのようなことを感じたか、お母様やお父様はどんなことを考えたのかを話し合ってみると、理解が深まっていくと考えられます。

お子さんがサピックスの授業や問題を解くなかで理解してきたことと、保護者の方の考えが異なっていても構いません。むしろ一つのことに対して多面的な考え方、見方ができることを学ぶ機会になりますね!
記述問題の答えを確認するポイント
こんな声が聞かれることがあります。

親が子どもの書いた答えを採点するのはちょっと難しくて……。
保護者の方が採点するのは確かに難しいことだと思います。ですので、「この答えは何点」というように正確に得点を出す必要はありません。先ほどこんなことをお伝えしました。
大切なのは「模範解答と比べて何が足りないか」を確認することです。
こうお伝えしてみたものの、「模範解答と比べて何が足りないか」を確認すること自体が実は難しいものだと感じることがあります。その一因は、記述問題の答えがどのように採点されているのかがわかりづらいことにあると思います。
そこで、以下に記述問題の答えを確認するポイントと書く(書き直す)ときのチェック項目の代表例を挙げてみたいと思います。「答えを確認するポイント」としましたが、「答えを書く(直す)ときのチェックポイント」と言い換えることもできます。「書くときのポイント」と「直すときのポイント」は同じです。
このポイントがわかれば、受験生本人の解答と模範解答をどのような視点で比較すればよいか、答えを書く(書き直す)ときにどのようなことの気を付ければいいかがわかります。
- 「理由」が書かれているか
- 「だれ」「なに」が書かれているか
- 指すもののない指示語が使われていないか
- 気持ち言葉・心情語が入っているか(特に物語文・文学的文章)
「理由」が書かれているか
記述問題の答えに入れやすく、得点にもなりやすいのが「理由」の要素です。シンプルな例を挙げみます。
たとえば、お子さんが以下のような答えを書いたとしましょう。
うれしかった。
塾に通いはじめたばかりの受験生は、「答えを書いてみて」と言われても何を書けばいいのかわからないため、このような答えを書くことがありますね。これはもちろん仕方ないことだと思います。ただ、これではなぜ「うれしかった」のかがわかりませんね。そこでうれしかった理由を入れてみます。
赤いスニーカーを買ってもらえたのでうれしい気持ち。
このように理由が一つ入るだけで、読み手の納得感が増します。また、グッと解答らしくなりますよね。当然、得点も高くなるわけです。

サピックスでは4年生までのテキストで、この「理由→気持ち」の流れをじっくり学習します。
「だれ」「なに」が書かれているか
まずは以下の文をご覧ください。
- すごい勢いで走ってきたため焦る気持ち。
- プレゼントをあげたらよろこんでもらえたので、うれしい気持ち。
- 泣かせてしまったので申し訳なく思っている。
一見、問題のない答案のようにも思えますが、それぞれの文には配点されているポイント(加点される要素)が入っていません。1番目の文については「だれが」が抜けていますね。2番目の文は「だれに」が抜けており、3番目の文は「だれを」が抜けています。
簡単に修正してみると以下のようになるでしょうか。
- 鬼がすごい勢いで走ってきたため焦る気持ち。
- 友達にプレゼントをあげたらよろこんでもらえたので、うれしい気持ち。
- 母を泣かせてしまったので、申し訳なく思っている。
「だれが」「だれに」「だれを」を入れました。これだけで読み手(採点者)に意味が伝わりやすくなりますよね。
同じように「なにが」「なにに」「なにを」が抜けてしまう受験生も多くいます。「だれが」「だれに」「だれを」が抜けてしまうのと同様、注意するといいですね。
指すもののない指示語が使われていないか
記述問題の答えのなかに指すものがない指示語が書かれている答案もよくあります。
それは自分にとっては些細なことであったが、太郎にとっては重大なことだとわかり、おどろく気持ち。
文頭に「それ」という指示語があります。指示語は文字通り「指し示す言葉」なので、この答案のなかに「それ」が指し示す言葉がないと、意味の通らない文になってしまいます。このように、指示語が指し示す言葉がない文を書いてしまう受験生は少なくありません。特に4、5年生以下で、国語の苦手な受験生に多い印象がありますので、注意したいですね。
気持ち言葉・心情語が入っているか(物語文)
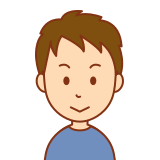
物語文の記述問題の答えには気持ち言葉(心情語)を入れるんだよ。
塾や家庭教師、個別指導の先生から、このようなことを教わっていると思います。
「物語」というと、「主人公がこうなって、ああなって……」というストーリー・あらすじを追うことが大切のようにも思えますが、そのストーリーを紡いでいるものは登場人物(つまり、人間)の感情です。ですから、物語文を読むときには、人物の感情をしっかり理解していく必要があります。
そうであれば、物語文の記述問題の答えには、基本的に人物の気落ち・心情をいれなければなりません。
ただ、こんなふうに感じてしまう受験生がいるかもしれません。
気持ち言葉を入れるんだよって言われるけれど、どこに入れればいいかわからない!
この気持ち、よくわかります。そこで私は特に5年生以下で国語の苦手な受験生には、このように答えています。

気持ち言葉を入れられそうなところには全部入れておけば大丈夫!
採点許容は中学校の先生方のお考えや方針によって異なりますので、ここにどの中学校の入試にも通用するたった一つの絶対的な採点基準を明記することはできません。ただ、記述問題の答案に明らかな間違いがない限り、書き過ぎて減点されることは考え難いな……と考えています(実際、このようにアナウンスしている中学校もあります)。ここで言う明らかな間違いとは、「本来は『うれしい』と書くべきところ、『悲しい』になっているようなところ」と考えると考えるとわかりやすいのではないでしょうか。このように明らかな誤りにならない限り、入れられそうなところにはすべて気持ち言葉を入れておくべきでしょう。
いっぽう6年生や国語の得意な子には、このように答えることもあります。

要素の最後には気持ち言葉を入れておくんだよ!
たとえば、以下の解答例をご覧ください。
戦乱のせいで息子のささやかな願いを叶えてかなえてあげられなかったし、大切な息子の命を奪った武将同士の争いに対してやり場のない怒りを覚えている。
この解答例を要素ごとに大きく分けると以下のようになります。
- 戦乱のせいで息子の願いを叶えてあげられなかった
- 大切な息子の命を奪った武将同士の争いに対してやり場のない怒りを覚えている
このように考えてみると、1つめの要素に気持ち言葉・心情語が入っていないことがわかります。
以下のように、気持ち言葉・心情語を入れてみます。
戦乱のせいで息子の願いを叶えてあげられなかったことに、親として申し訳なさや無力感を覚えるとともに、大切な息子の命を奪った武将同士の争いに対してやり場のない怒りを覚えている。
「親として申し訳なさや無力感を覚えるとともに」というように気持ちを表す表現をプラスしました。多くの場合、ここに配点されているのだと考えるといいですね。
さらに詳しい記述問題の解き方・書き方は?
記述問題の解き方・書き方・直すときのチェックポイントをさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
サピックスの国語で偏差値60を目指す家庭学習・宿題のポイント まとめ

サピックスで授業を受けてきただけでは不十分。家庭学習・宿題には必ず取り組みましょう!
国語Bの家庭学習は優先順位と手順に則って取り組みましょう!(本文を参考にしてくださいね!)
記述問題の答えを確認するポイント・解答を書くポイントをよく意識しましょう!
サピックスで国語の偏差値60を目指すのであれば家庭学習・宿題の取り組みは必須です。そのいっぽうで「国語の家庭学習ってどうやればいいのですか……」というご相談を受けることが多いのも事実です。今回紹介した家庭学習・宿題に取り組む際のポイントが参考になれば幸いです!
皆さんの中学受験が少しでもいいものになりますように!




_2-160x90.png)