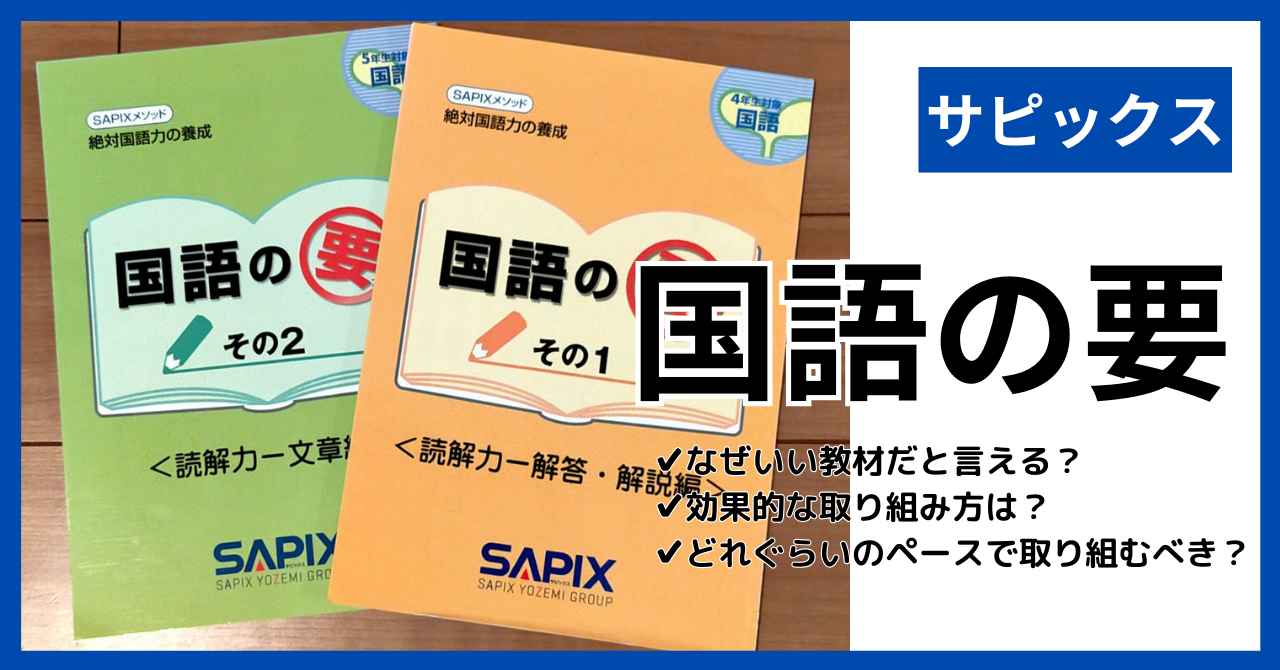サピックスでは4年生と5年生の夏に「国語の要」という副教材が配布されます。筆者は非常にいい教材だと考えているのですが、受け取ったご家庭、生徒さんとしてはどのように使えばいいのかわからず、書棚に眠ってしまうことがあるようです。実際、筆者が体験授業にうかがうと、「国語の要ですよね、配られたのですが、どう使えばいいのかわからなくて……」という声をよく聞きます。今回は国語の要の使い方、取り組み方を紹介します。
国語の要とは|サピックスが配布する副教材
国語の要は、サピックスの平常授業で使う「Daily Sapix(デイリーサピックス)」とは別に配布される4冊組の副教材です。4年生の夏に配られるのは黄色で「国語の要その1」、5年生の夏に配られるのは緑色で「国語の要その2」となっています。
内容は「国語の要その1」も「国語の要その2」も同じで、「読解力-文章編」「読解力-問題編」「読解力-解答・解説編」「知識力」の4冊で1セットです。
「読解力」の冊子の構成は4年生と5年生各20回ずつとなっており、文学的文章や説明的文章、随筆文がバランスよく配置されています。また、第1回から第20回と回数を重ねるごとにだんだんと文章が長くなり、難易度も上がっていきます。また、問題自体も記号選択問題、抜き出し問題、記述問題など入試や模試によく見られる問題がバランスよく配置されており、少しずつレベルアップできるよう設計されているのが特徴です。
「知識力」には、ことわざや慣用句、二字熟語や四字熟語、同音異義語や同訓異字、主語・述語・修飾語、接続語や指示語、敬語など、各学年で身につけておきたいことが掲載されています。
「国語の本質は読解問題である。知識は出題されない学校があるから、そこまでがんばらなくてよい」という意見を聞くことがありますが、本当でしょうか。知識力は読解力の土台となります。知っている言葉の数が少ないと、「本文のこのあたりに答えがありそうだな」と気付いても、そこに書かれている内容を読み取れません。また、本文中の言葉を言い換えた表現が選択肢にあっても気づくこともできません。さらに、記述問題の答えに自分の書きたいことを表現することもできませんね。やはり、言葉をたくさん知っているからこそ、答えをしっかり出せるのですね。

サピックスの6年生2025年4月度マンスリーテスト大問6では、本文中の「故きを温ねて新しきを知る」が傍線部となり、その言い換えが求められる問題が出ました。当然、この言葉の意味を知っていた受験生は、その意味をヒントにしてどんな答えになるかを予想できたはずです。いっぽう言葉の意味を知らなかった受験生はヒントをつかめずに答えを考えていくことになったと思われます。どちらが解答に有利かは明らかですね。このように言葉の知識の学習は、独立した大問だけでなく読解問題のなかでも非常に役立ちます。
「国語の要」をいい教材だと考える理由
冒頭にお伝えしたことと重複しますが、私は「国語の要」を非常にいい教材だと考えております。なぜでしょうか。
本文の読み方・問題の解き方を復習できる
まず、もっとも大きな理由は、解説が詳しいことです。各問題の解説には、「指示語の問題です」「場面分けの問題です」「理由を考える問題です」というように問題のカテゴリー・ジャンルが明記されており、「とき方のコツ」「書き方のコツ」「覚えておこう」「調べてみよう」というように問題のポイントが掲載されています。そのうえで図解などによって、本文のどこに注目すべきだったのかなどが解説されているという構成です。
これはサピックスに限りませんが、テキストやテストの解説に授業と同じレベルの詳細な説明が掲載されていることは多くないのではないでしょうか。詳細な説明を掲載するのはさまざまな観点からなかなか難しいことですので、仕方ないことだと思います。ただやはり「国語の苦手な子がこの解説を読んで答えにたどり着くのは難しいのではないか……。保護者の方が説明するにしても、国語の苦手な子が納得するだけの説明は難しいよなあ……」と感じてしまうことがあります。
こうしたなか、「国語の要」の解説は比較的丁寧に書かれていますので、「問題を解くときにはどのようなことに気を付ければいいのか」「どうしてその答えが正しいのか」を学習できるはずです。受験生本人だけで難しい場合は、保護者様も一緒に考えて理解させてあげるといいですね。

国語の授業と「国語の要」を両輪にするようなイメージを持っておきましょう。「国語の要」で学習したことは国語の授業でそのまま役に立ちますし、その逆もあります。こうしてつけた力が、各中学校の入試対策の土台となるのですね。
難易度が少しずつ上がっていく
「国語の要1」も「国語の要2」も全20回ずつで構成されています。そして、その難易度は少しずつ段階的に上がっていくのが特徴です。ですから、いきなり難しい問題を解かなければならなくなることもありませんし、学力がついているのに簡単な問題に戻ることもありません。教材の難易度の変化についていくことで、少しずつ学力を上げていくことができます。
典型的な表現や問題を経験できる
「国語の要」には入試によく設問とされる典型的な表現が多く出てきます。また、どのように解けば正解にたどり着けるかがある程度わかっている典型的な問題もよく出ます。
たとえば「国語の要」のある回のなかに、こんな問題があります。
傍線部⑦「ピーンと張った冷たい糸が、~巻きあげていく」とありますが、このときのるりの様子を答えなさい。
傍線部の「ピーンと張った」「糸」という表現は、「緊張」を表すことが多くあります。つまり、「るり」が緊張している様子であることがわかりますね。
この「ピーンと張った」という表現あるいは類似の表現は、小説や物語文では珍しい表現ではありません。この問題で一度、「ピーンと張った=緊張」と経験しておけば、次回以降に出題されたとき、こうした表現を見ただけで「緊張」なのだろうと推測することができるはずです。
「国語の要」には、このようなよくある表現について考える問題やよく出る問題が多く掲載されています。傍線部の前の指示語の内容を追っていけば答えが出る問題、対比を利用すれば答えを類推できる問題、時間・場所・登場する人物の変化に着目して場面分けする問題などなど、入試によく出るさまざまな問題を経験できるのです。こうした問題全40回分にしっかり取り組めば、大きな効果が期待できます。

「国語の要をやると成績が上がるのですか?」といった質問をいただくことがあります。もちろん取り組み方にもよりますが、国語の要に取り組むことで伸びていく生徒さんを目の当たりにしたことは何度もあります。一緒に学習している生徒さんから「あの子は国語の要をがんばったら成績が上がったんだって」と聞いたこともあります。効果的に取り組めば、国語力の上がる教材だと考えています。
「国語の要」の効果的な使い方、取り組み方
「国語の要」にはどのように取り組めばいいのでしょうか。まず大切なことは「本文」と「問題」をコピーして、プリントの形にして解くことです。
2つの冊子のまま解こうとすると、物理的に大きいため、4年生5年生にとっては扱いづらいことがあります。大きな冊子をめくるだけでもストレスになるので、それだけで取り組むのが負担になりかねません。コピーすれば文章と問題を合わせても5枚前後で済むので、こういった心配はなくなります。
保護者様にとっては毎回コピーを取る手間がかかってしまうのですが、ぜひコピーしてから取り組ませてあげてください。
そのうえで、具体的には以下のような手順で進めるといいですね。
- 目標時間内で問題を解く(本文右下に記載あり)
- 丸つけ
- 間違った問題の直し
- 正解した問題の確認
実際に受験生に解いてもらうと、制限時間内に終わらないことがあります。その場合は時間を延長して取り組んでもいいでしょう。制限時間20分の問題を40分かけて解くのはよくありませんが、5分~10分程度の延長であれば仕方ないと思います。スピードばかりを追求するのもよくありません。時間切れで解けない問題が出てしまうよりは、多少延長しても構わないので全部解くことを優先していいと思います。
また、制限時間内に解くのが難しい場合には、本文だけは音読してから問題に取り組むというのも一案です。黙読よりも内容が頭に入りやすいので、その後の問題を解きやすくなりますよ。
重要なのは「③間違った問題の直し」
問題を解き終わったら丸つけをして直しをします。その後、まずは間違った問題をしっかり確認しましょう。国語の要の解答解説編は問題の解き方や問題を解くためのヒント、注目すべき点がしっかり掲載されています。どのように考えれば正解にたどり着けたのかをしっかり確認しましょう。

間違った問題の確認の際に大切なのは、「内容的な観点」からだけで答えを出そうとしないことです。「内容的な観点」とはたとえば「主人公のAさんが友だちのBさんとケンカをした」というようなことですね。そうではなくて、文章を形から捉えるようにしましょう。たとえば、「設問とされる傍線部の前に『なので』があるからその前に理由が書かれているはずだよね」というようなことです。こうしたことができるようになると、別の文章でも同じような読み方ができるようになっていきます。
「④正解した問題の直しと確認」も重要
受験生と正解した問題について話していると、「実は勘でした」「最後2つの選択肢までしぼれたのだけれど、そこから先は適当に選んでしまった」ということがよくあります。こういった問題も必ず確認しておきましょう。確認の仕方は基本的に「間違った問題の直し」で構いません。

選択問題で2つまでしぼれた場合は、迷った2つの選択肢を比較すると答えを出しやすくなることがあります。2つの選択肢のどこが異なるのかを見つけたら、その部分について本文を確認すれば正解が出ることになります。「2つまでしぼれたけれど、最後は勘で答えを出してしまった」という場合は、試してみることをおすすめします。
「国語の要」に取り組む頻度は?
全20回ある問題をどれぐらいの頻度で取り組んでいけばいいでしょうか。筆者のおすすめは2パターンあります。そもそも「国語の要」は4年生の夏前と5年生の夏前に配布されるものです。「国語の要1」が配布されてから「国語の要2」が配布されるまでに1年の時間があります。
そこでまず一つめのパターンは、この1年間をフルに使って20回を終わらせる頻度で進める方法です。1年間を約52週間と考えると2.5週間に1回分ぐらいのペースで終わります。このペースであれば、比較的無理なく進められる可能性がありますね。
もう一つは、新学年になるまでに20回分を終わらせるパターンです。「4年生で配布された教材は4年生のうちに終わらせたい」ということであれば、こちらを選択することもありそうです。「国語の要」が配布されてから次の学年がスタートするまでは約半年あります。1週間に1本ぐらいのペースで取り組めば、20回分を終えられる計算になります。一つめのパターンと比較するとややスケジュール調整が大変になりますが、時間的に余裕がありそうであれば取り組める可能性はありますね。

まとめて5回分、10回分と取り組む受験生がいますが、筆者としてはあまりおすすめしておりません。上記でお伝えしたことと重複しますが、国語の授業と両輪をまわすこと、そして毎回の取り組みで設問の解き方を理解して直しをすることで、じっくりと力をつけていくべきだと考えています。時間をかけて長期的な視野で取り組みましょう。ちなみに、この考え方は6年生後期の過去問の取り組みにも通じるところがあります。
まとめ
「国語の要」は少しずつ難易度の上がる40回分の問題のなかで、本文の読み方・解き方を学べる非常にいい教材となっています。詳しく書かれた解答解説の内容を参考にしながら効果的に取り組み、平常授業のデイリーサピックスと両輪をまわすイメージで取り組むといいですね。