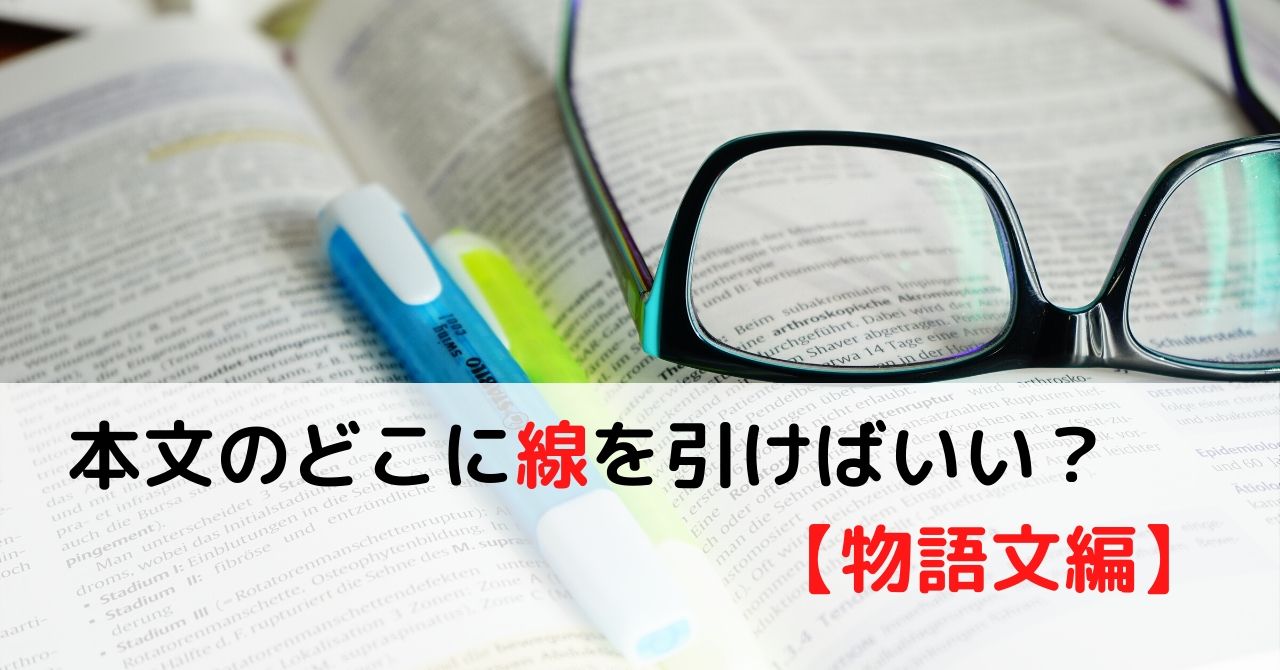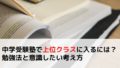「本文にしっかり線を引きましょう」
塾の講師から、こう言われたことのある受験生はかなりたくさんいるはずです。一方で、「こういうところに線を引くんだよ」と体系的に教わったことのある受験生はなぜか多くありません。
筆者は国語の家庭教師をしていますが、「国語の成績が伸びなくて困っています」というお子さんと会うと、本文や設問に線を引いていないことがよくあります。お話を聞くと「どこに線を引けばいいのかわからない」ということがほとんどです。それでは「しっかり線を引きましょう」と言われても困ってしまうのも無理はありませんね。
本文をしっかり読んで解答に活かすためには、どのようなところに線を引けばいいのでしょうか。この記事では「物語文」の基本的な線の引き方を説明します。
【論説文や説明文の線の引き方はこちらです!】
本文に線を引く理由
「線の引き方」を説明する前に、「線を引く理由」について考えてみましょう。
本文に線を引きながら読むと、そのせいで読むスピードが落ちてしまうことがあります。それにもかかわらず、なぜ線を引く必要があるのでしょうか。理由は主に2つあります。
1、線を引くことで、読みながら大事なところを意識できる
国語の苦手な受験生を見ていると、「メリハリをつけずに本文を読んでいるなあ」と感じることがよくあります。「このあたりは大切そうだな、この辺はあまり大切そうではないな」などと考えずに読んでしまうのですね。
線を引くと「ここが大切そうだな」と意識的に本文を読んでいくことができます。必然的に内容を考えながら読むようになるため、本文の理解も深まるのです。
2、効率的に問題を解ける
本文に線を引くことは、解答時間の短縮にもつながります。
線を引いていない受験生を見ていると、設問を読んだあと本文の戻るべき場所を探してページをペラペラめくっている様子をよく目にします。これでは設問のたびに時間的なロスが生じてしまい、効率的に問題を解けません。
しっかり本文に線を引いておけば、意識的に読んでいる分だけ「この内容はあの辺りに書いてあったよな」と考えられるようになります。本文に線を引くのは時間ロスになるように思えて、トータルで見れば時間の短縮につながるのです。
物語文で線を引いておきたい4つのポイント
それでは実際、本文のどのようなところに線を引けばいいのでしょうか。物語文で線を引いておきたいポイントを紹介します。
1、登場人物
まずは「登場人物」には必ずチェックを入れましょう。普通の傍線や波線でもいいのですが、筆者は目立たせるためにはじめて出てきた人物の名前は丸で囲うようにしています。
登場人物に線を引くのは「物語は人間の感情でできている」からです。言い換えると、「人物がなにかの感情になって行動した結果が物語になる」ということになります。
新しい登場人物が出てきたら、「タロウくんが主人公なんだな」「タロウくんの友人にハナちゃんがいるんだな」などと意識しながら読み進めましょう。
2、登場人物の性格や事情、境遇がわかるところ
登場人物の性格や事情、境遇がわかるところにもチェックを入れましょう。物語の登場人物は実際の世界にいる人間と同じだと考えてください。優しい人もいれば思いやり欠ける人もいます。裕福な家の子もいれば、経済的には恵まれていない子もいます。こうした性格や事情、境遇がわかるところには必ずチェックを入れるようにしましょう。
それでは、人物の性格や事情、境遇がわかるところに線を引くのはなぜでしょうか。それは性格などによって、出来事があったときの感情が違うからです。
たとえば、サッカーの試合に出場している少年が2人いたとしましょう。試合はすでに後半のアディショナルタイム。残り30秒ほどで試合が終了するような時間帯に、1点差で負けているような状況を想像してみてください。
こんなとき、負けず嫌いな少年は「あと30秒で必ず1点を取って、延長に持ち込む!」と考えるかもしれません。一方、闘争心の弱い少年は「もうダメだ……」とあきらめてしまうかもしれません。
このように同じ出来事に直面しても、性格が違えば感情に差が出ます。先ほどお伝えしたように「物語は人間の感情でできているもの」。感情の元になることが多い、性格や事情、境遇にはしっかり線を引いて、「この人物はこういう性格の子なのだな」と意識しながら読むようにしましょう。
3、人物の気持ちがわかるところ
中学受験塾の教室では、こんな会話が交わされます。
講師「物語文で大切なことはなんだっけ?」
生徒「(登場人物の)気持ちー!」
繰り返しますが、物語は人物の感情でできています。
「人物が出来事に直面する→嬉しい、悲しい、悔しいなどの気持ちが起きる→人物が行動する」という流れをイメージするとわかりやすいかもしれません。
「この人物はこのとき、こんな気持ちになったんだな。そして、こんなことをしたんだな」などと考えるためにも、人物の気持ちには線を引きましょう。

中学受験に物語文が出る理由を考えたことはありますか? 中学受験では一部の学校を除き、面接試験がありません。逆に言えば、学力だけで合格・不合格が決まってしまうわけです。この場合に困るのは「入学してくるのがどんな生徒かわからない」ということではないでしょうか。中学校としては、新入生のなかに「他者の気持ちがわからない子」がいたのでは困ります。そこで物語文を出題することで、他者の気持ちを理解できるかどうかを確認しようとしているのではないだろかと、筆者は考えています。
4、気持ちの変化がわかるところ
ほとんどの物語では人物の気持ちの変化が描かれています。「はじめはこんな気持ちだった人物が」「こういうきっかけで」「こんな気持ちになりました」という流れで書かれているわけです。
この気持ちの変化は、高い頻度で出題されます。たとえば駒場東邦は終盤に「心情の変化をふまえて」書く記述問題を用意することが多いですね。そうであれば、前半の気持ちから変化したことがわかるところがあれば、「最初はああいう気持ちだった人物が、こんな気持ちに変わったんだな」と意識するためにもチェックを入れるといいですね。
5、人物の精神的な成長がわかるところ
「4、人物の気持ちの変化がわかるところ」とよく似ているのですが、人物の精神的な成長がわかるところも非常に重要です。ジーニアスのG模試で、眞島めいりさんの「バスを降りたら」が題材になったことがあります。出題された部分のあらすじと一緒に、人物がどのように成長したか見てみましょう。
【あらすじ】
俺(古橋)は清瑛学園に通う中学1年生です。ただ、第1志望校だった峰森高校附属中に進学できず、高校受験で峰森高校に再チャレンジしようと考えています。
あるとき担任の藤町先生から、小学5年生向けの学校説明会で配るプリントを志鳥くんと一緒に作るよう頼まれます。ところが、清瑛に仕方なく通っている俺は、好きでもない学校を紹介しなければならないことに苦痛を感じていました。
ある日、その思いを志鳥にぶちまけてしまいます。「俺、清瑛なんかじゃなくて、峰森に通いたかった」
翌日。志鳥から聞かされたのは、志鳥が清瑛を希望して入学してきたことや、清瑛を希望するようになるまでのエピソードでした。
この話を聞いた俺は、ようやく気付きました。
俺にとって不本意な場所だとしても、別の誰かにとって同じだとはかぎらない。
志鳥くんにとって、ここは、通いたくて通ってる学校なんだ。
(略)
なんでもわかっている気になって、全然わかってなかった。傷つけられたことには敏感で、誰かを傷つけていることには鈍感だった。
ここが、人物の精神的な成長を読み取れる箇所です。「俺」は自己中心的な自分の考え方を認識したわけですね。
このあと清瑛や志鳥くんへの思いが大きく動き、学校生活が変化していくことだろうことを予感させるところで、出題の範囲が終わります。つまり、この精神的な成長を読み取れる箇所を境に、「俺」の心情が大きく変化していくわけです。人物の精神的な成長がわかるところに気付くことがいかに大切かわかりますね。
まとめ
物語文で線を引いておきたいところのまとめです。
- 登場人物
- 登場人物の性格や事情、境遇
- 登場人物の気持ちがわかるところ
- 気持ちの変化がわかるところ
- 人物の精神的な成長がわかるところ
物語文ではこうしたところにチェックを入れて、意識的に本文を読めるといいですね。ただし、線の引き方に客観的な100%の正解はありません。結果的に余分なところに線を引いてしまうこともありますし、逆に線が足りず(注目できていないところがあり)その後の問題で不正解になってしまうこともあります。何度も練習して自分なりの線の引き方、チェックの入れ方を確立していきましょう。
この記事はInstagramでもご覧になれます
Instagramでは、この記事に書かれていない情報もプラスしていますので、ぜひご覧いただければと思います。